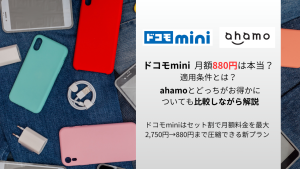「ゲームやYouTubeばかりで言葉使いが気になる」
「もっと語彙力をつけてほしい」
「ニュースにもっと関心をもってほしい」と願っている保護者は多いことでしょう。そんなときにぜひチャレンジしてみてもらいたいものとして家庭で手軽に読める 子ども新聞(小学生新聞)があります。
小学生新聞でおすすめは「朝日小学生新聞」「読売KODOMO新聞」「毎日小学生新聞」の3紙があります。毎日コツコツと読んでいくことで言葉の意味などに慣れやすく、ニュースや社会問題などの知識も自然と身に付けることができます。しかし、新聞はお子さんの読書習慣などで長続きしないことも多く、断念していることも多いです。お子さんの性格などに合わせて相性のよい新聞選びが重要となります。
最近では低学年でも読みやすい紙面づくりや図解・イラストが豊富な新聞も増えており、お子さんの“知りたい気持ち”を自然と引き出してくれます。紙の新聞はもちろん、アプリ版や電子版など生活スタイルに合わせて選べるのもうれしいポイントです。
この記事ではまず「子ども新聞とは?」という基本から選び方のポイントやメリット、そして読む習慣をつけるための工夫についてもまとめています。
これから購読を検討している方やどの新聞がわが子に合うのか迷っている方はぜひ最後まで目を通してもらえればと思います。
おすすめの子供新聞3選
| 読売KODOMO新聞 | 朝日小学生新聞 | 毎日小学生新聞 | |
| 月額料金 | 550円 | 2,100円 | 1.750円 |
| 発行頻度 | 毎週 | 毎日 | 毎日 |
| ページ数 | 20ページ | 8ページページ | 8ページ ※土曜は12ページ |
| 試読 | 1回分 | 3日分 | 1週間 |
| デジタル版 | 有り | 有り | 有り |
| 特徴 | エンタメ性が高く、週刊で読みやすい | 中学受験対策に最も強い | 時事問題・社会問題に最も強い |
読売KODOMO新聞

読売KODOMO新聞は2011年創刊の比較的新しい小学生向け新聞でありながら全国発行部数No.1を誇る人気紙です。毎週木曜日発行の週刊タイプのため、「毎日は読む時間がない」というご家庭でも負担が少なく、発行は週に1度と1週分の時事ニュースがまとまっているので、5年生や6年生などの忙しい時期のお子様におすすめです。1週間分の内容がまとめられているので最低限の知識を身に付けることができます。全20ページの構成で内容の充実度も申し分ありません。
紙面は大きめの写真やイラストを効果的に使ったビジュアル中心のレイアウトで、エンタメ性が高く、子どもが自然と読み進めたくなる仕掛けが満載です。名探偵コナンなどの人気キャラクターを取り入れた企画やポケモンの英語学習コーナー、学習塾講師による中学受験対策、科学特集など、幅広いテーマで時事ニュースや学習内容をわかりやすく届けています。
子ども新聞を初めて読むお子さん、新聞に苦手意識があるお子さん、楽しみながら読む習慣を身につけたいご家庭に最適。また中学受験を考えている場合にも、自然と学びにつながる内容が充実しているため特におすすめの一紙です。
キャンペーン期間中に読売KODOMO新聞の新規購読申し込みの方に【ポケモンドリル2冊】セットのプレゼントがあります!!
- ポケモンといっしょにおぼえよう!もっと四字熟語ドリルその2
- ポケモンといっしょにおぼえよう!熟語大百科ドリル①
キャンペーン期間:2025年11月28日(金)まで
- 新聞を読むのが初めて、またはあまり活字に慣れていない子。
- キャラクターや遊び感覚がある内容だと興味を持ちやすい子。
- 週1回で「読む習慣をつけたいが、毎日読むのはハードルが高い」という家庭。
- 週1回なので、毎日のニュースを追いたい場合は物足りない
- エンタメ要素が多い分、硬派なニュース量は他新聞より少なめ
- 中学受験対策としては朝日小学生新聞の方が評価が高い
朝日小学生新聞

朝日小学生新聞は1967年に創刊された歴史ある小学生向け新聞で、毎日届く日刊(8ページ)という読みやすいボリュームが魅力です。政治・経済・文化・科学など幅広いテーマを扱い、特に時事ニュースの分かりやすさには定評があります。そのため受験対策として購読するご家庭が多いのが特徴です。
なかでも人気のコラム「天声こども語」は季節の話題やニュースを子ども向けに噛み砕いて紹介するもので、語彙力・読解力の向上に役立つと高く評価されています。またマンガやエンタメ情報も盛り込まれており、飽きずに読み進められる工夫が施されています。
活字に親しんでいるお子さまや、毎日コツコツと学習を積み重ねたいお子さまに相性が良い新聞です。特に読解力・作文力を伸ばしたい場合や、低学年のうちから本格的に時事問題に触れさせたいご家庭におすすめです。
- 毎日のニュースに触れたい、継続して読む習慣をつけたい子。
- 中学受験を視野に入れている家庭。時事問題理解や考える力を育てたいときに強みがある。
- 新聞を読むことで表現力や思考力を鍛えたい子。親子で議論したり、記事づくりに関わるのが好きな子にも向く。
- 広告の量が他紙と比べると多い
- 受験を考えていない家庭には合わない場合がある
毎日小学生新聞

毎日小学生新聞は1936年創刊と歴史が長く、子ども向け新聞の先駆け的存在です。平日は8ページですが土曜日は12ページとボリュームが増えるため読みごたえがあります。
内容は最新ニュースも多くのジャンルを毎日取り扱っており、社会・経済やコラムなど幅広いジャンルで、とにかく内容を読ませるための工夫がされています
また考える力を育てる記事が充実しており、「てつがくカフェ」のように思考を言葉で整理する練習ができるコーナーは入試で求められる論理的思考力の向上にも役立ちます。
さらに読者参加型の企画も多く、職業体験やものづくりイベントなど親子で楽しめる実体験の機会が豊富なのも魅力です。
読書が好きでじっくり読み進めるタイプのお子さま、活字に慣れている高学年のお子さま、自分で調べたり深く考えたりすることが好きな子には特におすすめ。体系的に知識を伸ばしたいご家庭にも最適な新聞です。
- じっくり考えるのが好きな子、落ち着いた内容を好む子。
- 社会や教科を横断して学びたい、学習習慣として新聞を取り入れたい家庭。
- 中学受験を見据えつつ、時事問題や論理的思考を自然に育てたい子。
- ボリュームのある構成なので、毎日読み切れない子どもには向かない
- 少し地味なレイアウトなので読書が苦手な子どもは読みにくいかも
そもそも子ども新聞とは?内容や読ませる年齢について

子ども新聞とは主に小・中学生を対象に発行されている新聞のことです。
通常の一般紙(大人向けの新聞)が持つ「社会の動きを正確に伝える」という役割を維持しつつも、子どもが理解しやすいように内容、表現、レイアウトにおいて工夫が凝らされている点が最大の特徴です。
子ども新聞の内容
一般的には次のような内容が含まれます。
全体的に「難しいニュースを、子どもが理解しやすい形で伝える」ことに重点が置かれています。
- 時事ニュース
国内外の最新の出来事を子どもにもわかる言葉で解説したニュース。 - 社会・経済の仕組み
お金の動きや政治の仕組み、社会がどう回っているかをやさしく説明。 - 科学・自然
最新技術や宇宙、環境問題、動植物などを実験や写真で解説する。 - 文化・スポーツ・芸術
プロの活躍や映画、音楽、伝統文化などを紹介し、興味を広げる。 - 娯楽と親しみやすいコンテンツ
漫画、パズル、クイズなど、楽しみながら活字に親しむための記事。 - 読解力・語彙力を伸ばすコラム
言葉の意味や文章の読み方を学べる短い解説記事や問題。 - 自由研究や学習に役立つ企画
工作、実験、観察記録のヒントなど、勉強や宿題に使えるテーマを紹介。 - 職業紹介・キャリア教育
様々な仕事の内容や働く人の思いを紹介し、将来を考えるきっかけを提供する。
子ども新聞は何歳から読むのがベスト?

子ども新聞を読み始めるタイミングとしては一般的に小学校中学年(3〜4年生)頃が最も適していると言われています。
この時期は文章への抵抗が少なくなり、時事ニュースや社会の仕組みといった少し難しい内容にも興味を持ち始めるため理解度も深まりやすいのが特徴です。
ただし子ども新聞は小学校1年生からでも読めるように工夫された紙面になっており、写真や図解が多く使われているため低学年でも楽しむことは十分可能です。
とはいえすべての内容を自力で理解するのはまだ難しいこともあるため、最初のうちは保護者が読み聞かせる・一緒に記事を読むなど、サポートをしながら進めるとより効果的です。
お子さんの興味や読む力に合わせて無理なく楽しく取り入れていくことが大切です。
子ども新聞を選ぶポイント

子ども新聞を選ぶ際は次の3つのポイントを押さえておくと失敗しにくくなります。
- 発行頻度とボリューム
- レイアウトとデザイン
- 購読料と付帯サービス
発行頻度とボリューム
子ども新聞を選ぶときはまず発行頻度と情報量が子どもの学習習慣に合っているかを確認しましょう。
新聞には毎日届く日刊紙と週に1回届く週刊紙があります。日刊紙はニュースの速報性が高く、受験対策などで集中的に知識を身につけたい場合にぴったりです。一方週刊紙は情報が整理されていて量もちょうどよく、習い事で忙しいお子さんでも無理なく読み切れるのが魅力です。
子どものスケジュールや負担の大きさを考えて、続けやすい頻度を選ぶことが大切です。
レイアウトとデザイン
新聞の見た目、つまりレイアウトやデザインは子どもが「読んでみたい!」と思えるかどうかに直結するとても大切なポイントです。
大人向けの文字がびっしり詰まった新聞とは違い、子ども新聞は写真やイラスト、図解が豊富かどうかをチェックしましょう。紙面がカラフルで見やすく、文字の大きさや行間も読みやすいかどうかも重要です。漢字にはすべてふりがながついているかも確認してください。
読むこと自体が楽しく知的好奇心を刺激してくれるデザインであれば、新聞を読む習慣を自然に身につけやすくなります。
購読料と付帯サービス
子ども新聞を選ぶときは費用対効果や付加価値も大切なポイントです。
まず日刊紙と週刊紙では購読料が大きく違うので、ご家庭の予算に合っているか確認しましょう。また最近の子ども新聞は紙面だけでなくさまざまなサービスも提供しています。
例えばタブレットやスマホで読めるデジタル版があるか、読者向けの体験イベント(記者体験など)やプレゼント企画があるかなどです。デジタル版は外出先でも読めて便利ですし、イベントはお子さまの興味やモチベーションを高める効果があります。
価格だけでなく、こうしたサービス全体で比較して選ぶと満足度が高くなります。
子ども新聞を読んでえられる効果6つ

子供新聞を読んで得られる効果について説明します。
- 文章を読む習慣をつけられる
- 中学受験に便利
- 親子の会話が増える
- 語彙力が身につく
- 時事ネタ・ニュースに触れられる
- 好きなことを見つけるきっかけになる
文章を読む習慣をつけられる
子ども新聞を毎日または定期的に読むことで自然と文章に触れる時間が増え、読む習慣を身につけることができます。
短い記事や図解入りの記事が多く、難易度も子ども向けに調整されているため読書が苦手なお子さんでも無理なく取り組めます。毎日読むことで文章を読み解く力や集中力も少しずつ養われ、学校の授業や宿題にもスムーズに取り組める土台作りになります。
中学受験に便利
子ども新聞は特に中学受験を控えているお子さんにとって最強の「生きた教材」になります。
入試では社会や理科、国語といった教科に関わる時事問題が頻出しますが、子ども新聞は最新のニュースを小学生が理解できるレベルでしっかり解説してくれます。毎週ニュースの背景や仕組みを整理して読むことで、塾のテキストだけでは補えない「社会で今何が起きているか」を理解する力が自然に育ちます。
受験対策としてもぜひ手元に置きたい強力な味方です。
親子の会話が増える
子ども新聞を読むことで家庭内での会話のきっかけが増えます。
ニュースや記事を一緒に読んだり、「これはどういう意味?」と質問を受けたりすることで親子で意見交換ができます。日常的な会話に加えて社会問題や科学の話題も自然に共有でき、子どもが自分の考えを言葉にする練習にもなります。
親子のコミュニケーションが深まり、知的好奇心を刺激するきっかけにもなります。
語彙力が身につく
子ども新聞を読むことは楽しみながら語彙力をぐんぐん伸ばせる近道です。
記事には普段の学校生活や会話ではあまり使わない社会や科学の専門用語や少し難しい表現が自然な文章の中で登場します。しかもすべての言葉にふりがながついているので、辞書を引かなくても意味を推測しながらスムーズに読めます。
こうした積み重ねが表現力や作文力の土台になり、将来的には大学受験や社会に出たときの文章力にも大きく差が出てきます。
時事ネタ・ニュースに触れられる
子ども新聞を読むと社会への窓がぐっと広がります。
普段の生活ではあまり関わりがないように思える政治や経済、国際問題も新聞を通して「自分たちとどうつながっているか」がわかるようになります。テレビのニュースでは流れてしまう情報も、新聞なら背景や仕組みまで丁寧に解説されているので、「なぜそうなったのか」をしっかり理解できます。
これによって社会への関心が高まり、少し先の広い視野を身につけることができるようになります。
好きなことを見つけるきっかけになる
子ども新聞は様々な連載や特集を通じて、子どもたちの隠れた興味や才能を発見するきっかけを与えてくれます。
たとえば科学の最新研究、環境問題、プロの職業紹介、世界の珍しい文化など教科書だけでは出会えない多様なテーマが紹介されています。「この記事面白そう!」と夢中になる記事に出会うことで、将来の進路や趣味につながるような新しい知識の扉が開くことがあります。子どもがどんな分野に興味を持つか親が気づくためのヒントにもなります。
新聞を読む習慣をつけるためには

新聞を読む週間をつけるための方法を2つご紹介します!
- 親子で一緒に読む
- お気に入りのコーナーを見つけておく
親子で一緒に読む
新聞を読む習慣を身につけるには親子で一緒に読むことが効果的です。
小学生にとってひとりで新聞を読むのは少しハードルが高いこともありますが、親と一緒に読むことで理解しやすくなり、読む楽しさも感じやすくなります。
例えば朝の朝食時に一緒に記事を読んで「今日のニュースはどう思う?」と会話するだけでも自然に新聞に触れる時間が増えます。また親が読み方や記事のポイントを説明してあげることで、子どもは難しい内容でも理解しやすくなり、読解力や考える力の向上にもつながります。親子で楽しみながら続けることが、習慣化のコツです。
お気に入りのコーナーを見つけておく
新聞を読む習慣を続けるためにはまずお子さんが「読むのが楽しい」と感じるお気に入りのコーナーを見つけることが大切です。
スポーツ、科学、動物、文化など、興味のあるテーマから始めると自然と集中して読む時間が増えます。毎回そのコーナーから読んでいくルーティンを作ると読む習慣が無理なく身につきます。
また興味のある内容について親子で話し合ったり自分で調べてみるとさらに理解が深まります。
お気に入りコーナーを入り口にすることで新聞が「学びの道具」だけでなく、楽しみながら情報を得られるツールになります。
読売KODOMO新聞・朝日小学生新聞・毎日小学生新聞それぞれ向いている人

最後に読売KODOMO新聞・朝日小学生新聞・毎日小学生新聞がそれぞれどんな子に向いているかをわかりやすくまとめました。
無料お試しも手軽で便利ですが、実際の良さをしっかり感じるには1ヶ月だけでも購読してみるのがおすすめです。続けて読むことで内容の魅力がより深くわかり、記事の流れやテーマの幅広さも実感できます。
ぜひ気軽な気持ちで始めてみてくださいね。
読売KODOMO新聞が向いている人:ニュースをやさしく楽しく学びたい子
読売KODOMO新聞は内容がやさしく、写真・図解・イラストが多いのでコンパクトで読みやすく、「新聞が初めて」という子にピッタリ。
また週1回の発刊なので習い事や塾で忙しい子、毎日発行の新聞が溜まってしまうのが心配な家庭にもおすすめです。
朝日小学生新聞が向いている人:読む力・考える力をしっかり伸ばしたい子
朝日小学生新聞は毎日発行で情報量が多く、教科に役立つ知識、社会問題、時事解説、読解力を鍛えるコラムが充実しています。
中学受験の対策として使う家庭も多く、学習意欲が高い子・読書が好きな子・中学受験を視野に入れている子に特に向いています。
毎日小学生新聞が向いている人:ニュースを幅広い視点で学びたい子
毎日小学生新聞はやさしいニュース解説に加えて、国際問題、科学、文化、SDGsなど“社会の広いテーマ”をバランスよく取り上げるのが特徴。興味の幅を広げたい子向け。
文章が比較的やさしく、ニュースや学習企画もバランスよく取り上げられるため、無理なく読み続けたい初心者〜中級レベルの読者に特に向いています。
子ども新聞のよくある質問

- 子ども新聞はコンビニで買える?
-
残念ながら多くの子ども新聞はコンビニエンスストアでは基本的に販売されていません。
子ども新聞は一般紙と同様に新聞販売店からの定期購読が主な購入方法となっています。そのため「ちょっと試しに一冊だけ」とコンビニに立ち寄っても、店頭に並んでいることはほとんどありません。
もし試しに読んでみたい場合は各新聞社のウェブサイトから「無料見本紙」を請求するのが一番確実で簡単な方法です。また駅の売店や大きな書店の一部店舗で取り扱いがある場合もありますが、確実に入手するには定期購読をおすすめします。
- 子どもが興味を持たない場合はどうすれば良い?
-
子どもが新聞に興味を示さない場合、無理に読ませるより「楽しさ」を伝える工夫が大切です。
例えば興味があるテーマの記事から一緒に読んでみる、親子で感想を話す、イラストや写真が多いページから始めるなど工夫すると自然に関心が湧きます。また読んだ記事をもとにクイズや会話をしてみると、学ぶ楽しさを実感しやすくなります。小さな成功体験を積み重ねることで、少しずつ自分から新聞を手に取るようになります。
- 子ども新聞はコンビニで買える?
-
残念ながら多くの子ども新聞はコンビニエンスストアでは基本的に販売されていません。
子ども新聞は一般紙と同様に新聞販売店からの定期購読が主な購入方法となっています。そのため「ちょっと試しに一冊だけ」とコンビニに立ち寄っても、店頭に並んでいることはほとんどありません。
もし試しに読んでみたい場合は各新聞社のウェブサイトから「無料見本紙」を請求するのが一番確実で簡単な方法です。また駅の売店や大きな書店の一部店舗で取り扱いがある場合もありますが、確実に入手するには定期購読をおすすめします。
- 子どもが興味を持たない場合はどうすれば良い?
-
子どもが新聞に興味を示さない場合、無理に読ませるより「楽しさ」を伝える工夫が大切です。
例えば興味があるテーマの記事から一緒に読んでみる、親子で感想を話す、イラストや写真が多いページから始めるなど工夫すると自然に関心が湧きます。また読んだ記事をもとにクイズや会話をしてみると、学ぶ楽しさを実感しやすくなります。小さな成功体験を積み重ねることで、少しずつ自分から新聞を手に取るようになります。
- 読む時間が取れない場合はどうしている?
-
習い事などで忙しいお子さんの場合、毎日時間を確保するのは大変ですよね。そんな時は「スキマ時間」を上手に活用しているご家庭が多いです。
例えば夕食の準備ができるまでの5分間、学校に行く前の朝の10分間、寝る前の布団の中など無理なく集中できる短い時間で、気になる記事だけを読むようにしましょう。また週刊紙を選ぶことで週末に時間を確保してじっくり読むという方法もあります。
すべて読み切る必要はなく、「少しでも毎日活字に触れる」ことを最優先に考えてみましょう。
- 子ども新聞は図書館で読める?
-
地域によって異なりますが、多くの公立図書館や学校図書館では子ども新聞を購読しており自由に読むことができます。
自宅で定期購読する前に「どんな内容か試してみたい」「複数の新聞を比較したい」といった場合、図書館は最適な場所です。過去の新聞も保管されている場合があり、特定のテーマの時事ネタを調べたり、夏休みの自由研究の資料として活用したりすることも可能です。
図書館の開架スペースや閲覧室で気軽に手に取ってみることをおすすめします。
ただし館内での閲覧専用で持ち帰ることはできません。子ども新聞を継続的に読みたい場合は、定期購読の申し込みが最も確実で便利です。
- デジタル版の子ども新聞はある?
-
最近では多くの子ども新聞がデジタル版やアプリを提供しており、忙しい現代の子どもたちにとって非常に便利です。
デジタル版のメリットは新聞が届くのを待たずに最新の記事をすぐに読めることや、外出先や移動中でもタブレットひとつで手軽に読める点です。
さらに紙面を拡大できるため、文字が苦手なお子さんにも優しい設計になっています。家庭によっては自宅では紙面でじっくり読み、外出先ではデジタル版でチェックするなど紙とデジタルを上手に使い分ける方法も増えています。
まとめ

子ども新聞はお子さんが楽しみながら知識を広げ、考える力を育ててくれる心強い学習ツールです。
ニュースだけでなく図解やマンガ、教育コラムなども充実しているため、活字が苦手な子でも自然と読み進められます。また日常の会話のきっかけが増えるのも子ども新聞の大きな魅力。家庭でのコミュニケーションが増えることで、学びへの意欲もさらに高まっていきます。
どの新聞を選ぶかは内容のやさしさ、興味を持ちやすいテーマ、続けやすい価格などがポイントになります。まずは試読を利用して、親子で「読みやすい」「続けられそう」と思えるものを選ぶのがおすすめです。
子ども新聞は今日からでも始められる未来への投資。ぜひお子さんの新しい学びの習慣づくりに、気軽に取り入れてみてください。